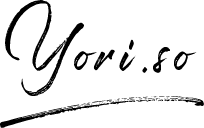be sensitive & effectual.
社長なのに、傷つきやすい。
それがぼくのコンプレックスでした。
その日も何気なく、友人にそんなことを冗談まじりで話していたときに、
その友人は「あなたのその繊細さは素敵だとおもう、直さなくていい」という言葉と一緒に、茨木のり子さんという詩人の「汲む」という詩を教えてくれました。
そこに書かれていた一節に、ぼくは衝撃をうけたのです。
“子どもの悪態にさえ傷ついてしまう
頼りない生牡蠣のような感受性
それらを鍛える必要は少しもなかったのだな
年老いても咲きたての薔薇 柔らかく
外にむかってひらかれるのこそ難しい
あらゆる仕事
すべてのいい仕事の核には
震える弱いアンテナが隠されている きっと……”
弱い心は、克服すべきもの。
心のどこかでそう思っていたぼくを救うような言葉でした。同時にそれはきっと、ぼくがずっと誰かに言って欲しいと思っていた言葉だった、
と思うのです。
yori.so gallery & labelは、ぼくのそんな原体験から生まれた、
人の心の中にある繊細さを、自分や他人を傷つけるためではなく誰かによりそうために使う生き方=sensitive & effectualな生き方をささえるために始まったギャラリールーム、レーベルです。
ふるえるこころは、おくりもの。
あなたがそう思える日がくるまで。
それがぼくのコンプレックスでした。
その日も何気なく、友人にそんなことを冗談まじりで話していたときに、
その友人は「あなたのその繊細さは素敵だとおもう、直さなくていい」という言葉と一緒に、茨木のり子さんという詩人の「汲む」という詩を教えてくれました。
そこに書かれていた一節に、ぼくは衝撃をうけたのです。
“子どもの悪態にさえ傷ついてしまう
頼りない生牡蠣のような感受性
それらを鍛える必要は少しもなかったのだな
年老いても咲きたての薔薇 柔らかく
外にむかってひらかれるのこそ難しい
あらゆる仕事
すべてのいい仕事の核には
震える弱いアンテナが隠されている きっと……”
弱い心は、克服すべきもの。
心のどこかでそう思っていたぼくを救うような言葉でした。同時にそれはきっと、ぼくがずっと誰かに言って欲しいと思っていた言葉だった、
と思うのです。
yori.so gallery & labelは、ぼくのそんな原体験から生まれた、
人の心の中にある繊細さを、自分や他人を傷つけるためではなく誰かによりそうために使う生き方=sensitive & effectualな生き方をささえるために始まったギャラリールーム、レーベルです。
ふるえるこころは、おくりもの。
あなたがそう思える日がくるまで。
yori.so gallery & label 主宰
高崎健司



エミリー・ディキンソンは、南北戦争の時代を生きたアメリカの詩人です。 生涯を自然の中の家の中で白いドレスを着て過ごし、ほとんど外にでることがなく、窓から差し込む光を頼りに詩作を続けました。
わたしたちはその生き方から、自分の心の中にある壊れそうなものを現実世界の棘のようなものから守りたいという気持ちと、それでも創作を通じて現実世界と関わりたいという祈りのような気持ちの両方を感じます。
そうしてその生き方から着想し、1つの映画と2つのドレスが生まれました。
moreわたしたちはその生き方から、自分の心の中にある壊れそうなものを現実世界の棘のようなものから守りたいという気持ちと、それでも創作を通じて現実世界と関わりたいという祈りのような気持ちの両方を感じます。
そうしてその生き方から着想し、1つの映画と2つのドレスが生まれました。